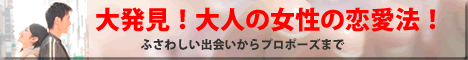共依存と全通の意外な共通点
()
3日目の朝を迎えました。
今日はいよいよ最終目的地の糸魚川を目指します。
姫川温泉の標高は260mで、前日の白馬から450mほど下ってきたのですが、
まだまだ気を抜くことはできません。
夜中はカメムシに悩まされましたが、
朝起きてみるとカメムシの影も形も無く、どこかに消えてしまいました。
あいつらも夜行性なんだろうか。
朝食を食べて、ロビーから糸魚川行きの列車を見送り、
出発準備を整えて、旅館を出発しました。
ここの宿はもともと客室が20室以上ある、わりと大きな旅館(ホテル)です。
しかしながらスタッフは、見る限り夫婦2人とお手伝いさん1人しかいませんでした。
そりゃ電話に出られなきゃ、フロントで待ちぼうけもするわけです。
この日の泊まり客は十数人ほどだったようですが、
それでも結構忙しかったのではないでしょうか。
[1日目・2日目の記録はこちらから]
3日目・5月5日(金・祝) 歩行区間:平岩-糸魚川 天気:晴れ
宿(8:25発)-平岩(8:33着・8:49発)-小滝(10:33着)-
まずは姫川を渡って、昨日素通りした平岩駅へ向かいました。
ここから先はずっと新潟県です。
平岩駅に着きました。
こちらはコンクリート造の頑丈な駅舎でした。
ホームは1面1線の片ホーム式ですが、
朝夕に平岩折り返しの列車があるため、出発信号機が設置されています。
ホームの形状からも分かるように、10年ほど前までは列車交換が可能でした。
写真中央の列車接近案内にその名残がうかがえます。
ホームから駅舎へ向かうとき、この通路を通ります。
今は殺風景な通路になってしまいましたが、
かつては待合室へとつながる引き戸(写真右奥)の近くに、
温泉地の駅ではおなじみの「周辺の旅館案内」がつり下げられていました。
さて、次の駅は小滝駅です。
「塩の道」は、平岩駅手前から小谷村の大網(おあみ)集落、
そして大網峠を経由して根知方面に直行するルートのため、通ることができません。
そのため、当初は平岩駅北西の大峰峠を経由するルートを歩くつもりだったのですが、
冬期通行止めがなかなか解消されないため、やむなく国道を歩くことにしました。
国道には5km以上にわたって延びる連続スノーシェッド区間があります。
無事通過できることを祈るばかりです。
まずは国道へと向かいました。
国道に合流しました。
少し進んだところから振り返ってみました。
姫川温泉は川の左側奥に、平岩駅は川の右側奥にあります。
意外にも、国道には歩道がありました。
それなら楽勝と思っていたのですが…
そんな期待はあっさり裏切られてしまいました。
まぁ、そんなこったろうと思ってましたよ。
姫川災害(7.11水害)復旧事業竣工記念碑の隣に、こんな大きな石が乗っていました。
その時の土石流で運ばれた岩なんでしょうか。
茶臼トンネルが見えてきました。
ここから先は、5km以上にわたる連続スノーシェッド区間です。
連続スノーシェッド区間に突入しました。
見渡す限り、どこまでもスノーシェッドが続いていました。
路肩がしっかり歩道代わりになっているように見えますが、
前半を中心に段差がなくなる場所が多々見られ、
危なそうな場所では何度か左側の路肩を歩きました。
スノーシェッド区間には、緊急脱出口が何カ所かあります。
写真右側、姫川の対岸に道路が続いていますが、
こちらは工事関係車両専用の道路で一般人は立ち入りできません。
連続スノーシェッド区間も半分を越えました。
所々で口を開けている緊急脱出口は、ほんとオアシスみたいな場所です。
撮り鉄の穴場になりそうな場所もあったりと…。
スノーシェッドのままトンネルをくぐりました。
トンネルを越えても、スノーシェッドは続いていました。
対岸を大糸線が併走するようになりました。
お互いスノーシェッドの中を走っています。
このあたりは姫川渓谷と呼ばれていますが、
いかに厳しい場所であるかがよく分かります。
やがて右手に大糸線の第4下姫川橋りょうが見えてきました。
7.11水害では鉄橋ごと流されてしまったそうです。
いよいよ小滝トンネルが見えてきました。
このトンネルを抜ければ、長かった連続スノーシェッド区間も終わりです。
トンネルを抜けてまもなく、小滝駅に到着しました。
こちらは大糸線が全通するまで、大糸北線の終着駅でした。
7.11水害の後も、2年あまりにわたって終着駅の役割を担いました。
現在、駅前には発電所の建物以外目立った建物は無く、
しばしば秘境駅のひとつに数えられています。
線路はホーム外側に引かれています。
現在は1面1線の片ホーム式として使用されていますが、
10年ほど前までは交換可能な島式ホームとして使用されていました。
中土駅同様、島式ホームにしては随分狭いホーム幅です。
自分が初めてここに来た時は線路がちゃんと2本ありました。
片方無くなってしまうと、なんだか寂しいです。
糸魚川行きの列車が到着しま�
��た。
列車からは2人ほど降りてきましたが、いずれの方も駅訪問が目的だったらしく、
10分ほど後に来た南小谷行きの列車に乗ってしまいました。
こちらもそろそろ次を目指したいと思います。
()
平岩駅から小滝駅までのGPSログ(1/60,000)です。
国道は姫川渓谷に沿うように走っています。
当初は地図左側を回って小滝駅へ向かう黄色い道を歩く予定でした。
アップダウンが大きい道のようですが、どんな道だったんでしょうね。
実はここにも全通
全通 平和で恋がいちばん。
遅い夏休みを戴いた。昨日は一日ゴロゴロし、良い休息とはなったが、たった1日で飽きてしまったので、今日はこんな、休日には混んでいてのんびり出来ない場所へとやって来た。勿論年間パスポートを持っているので交通費以外はかからない。
がしかし、この日は幼稚園の団体が3組位入っており、館内はごった返し、喧騒の渦と化していた。
リニューアル後、初めて訪れた模型運転場。園児達によって満席となっていたが、貸切ではなかった為、最後部から立ち見。峠を攻める鉄道がテーマとされており、碓氷峠やスイッチバック、ループ橋などが紹介されていた。車両が動き出したりプロジェクターに投影されたりする度にあがる園児達の黄色い声には心洗われた。馬鹿みたいな大声の独り言で自分の知識をさらけ出すおかしな大人とは雲泥の差である。
終演後、すぐ近くから運転場を見学。鉄博新都心駅の下で信号待ちをするカウンタックLP500R!(笑)
C57を前補機に従えたC62牽引の旧客列車の隣には、お馴染みのEH500牽引のコンテナ貨物。後ろの方には四季島やスペーシアといった、これまた見慣れた車両が並ぶ。
前回訪れた時には既に設置が済んでいたE1系。下から見上げるとまるで「壁」だったが、それを今回は新館へと通じる通路の上から見下ろす。
新館の目玉である初代山形新幹線の400系と現行のE5系。こちらは「モック」との事なので、床下に注目したい所だが、線路際まですっぽりと覆われている為、のぞきこむのは一苦労。一応車輪はある事だけは確認出来たが、「台車」があるかどうかは判らなかった。
新館の大部分は子供向けテーマパークのような内容であり、失望をかくし切れなかったが、ココ3階だけは別。歴代の駅施設が時代別に並ぶ。さすがの幼稚園児達もココまで上ってくる元気はないのか、優雅で上品な大人の空間が広がっていた。
黎明期のコーナーに置かれた電鍵。ハイモンドではなくGHDキーの現行品だ。早速触れてみるものの、ギャップが広すぎる。(勝手に)調整しようとしたのだが、固くて回らなかった。そして発信機がついていないので、一般人には何が何だか判らない展示となっている。
昭和初期の時刻表が閲覧出来る。山陰本線がまだ全通していない中、三江線の一部は既に姿を現している(といっても石見川越までだが)。
3シリンダー機C53のグレズリー式弁装置の超精密な模型。だが矢印部のピンにガタがある為、中央シリンダーの給排気弁がほぼまったく動かない(これは交通博物館時代から修理されていない)。普通のヒトには単なる蒸気機関車の足回りの模型としか見られないだろう。
昭和40年代の駅の様子。この時代はギリギリなんとか記憶がある。懐かしい。駅や改札の様子が数世代にわたり再現されている。
かつてはヒストリーゾーンに展示されていた初期のマルス。大掛かりな装置だが、おそらくはファミコンよりも低性能。初期のマイコンキット並みだろう。そんな所が素晴らしい。
我が家にあった1972年の時刻表に、「急行ニセコ」の名が記されていたような気がして、「あのニセコか!」と思って調べようとした時には既に廃棄された後だった。それと同年代の時刻表があったので見てみるとやはり載っていた。だが後で調べてみると、ニセコのSL牽引は昭和46年で終了しており、その後はDD51が充当されたとの事。それでも今から思えば夢のような光景だ。
1980年代の電子連動装置。駅構内のポイントや信号機を操作する装置だ。キー配置のおかしなPC-8801のようだ(笑)。
やはり1980年代製と思われる業務用パソコン。一部の人達が泣いて喜ぶ沖電気製。鉄道博物館にいながらコンピューターの歴史も巡る事が出来る?!
かつての特急車両を使用した休憩所も、開館後数度に渡る移動を経て、新館への通路の下に押し込まれた。これでもう移動する事も出来なくなった。通い慣れたてっぱくであるが、それでも3時間近くは堪能出来た。新館建設に伴い入場料が値上げされ、年間パスポートは更に割り増しの5000円となった。ちょっと次回の更新はしんどい。
13:23、歩いて大宮駅へと向う途中で恒例の1本!(笑)
14:52、大宮駅で6087列車を迎え撃つ。いつもの2071列車の1時間後をゆく。冬季に湯沢エリアで狙うとヘッドライトしか写らない。
15:02、
15:24、高崎線内では安中貨物と対で撮影する事の多い8883列車。熊谷付近で安中貨物に追い越される模様。
800両程あるタキ43000シリーズの中で唯一のステンレス無塗装のタンク体を持つタキ143645。もう何度も言っているが、飲料系のステンレスタンクローリ同様の鏡面仕上げにしてもらいたい!(笑)
15:36、安中貨物到着。ココで乗務員の交代がある。文字通りの「ココで」だ。線路上をヒトが歩いていると、たとえ関係者でも近年はちょっとハラハラする。
16:08、さいたま新都心駅の傍に、後位にメタノールコンテナが載せられたコキ200が繋がっている列車をみつけたので下車してみる。A203仕業の根岸【5160】川崎貨物【臨8763】倉賀野行きのようだが、当地を発つのは18時過ぎ、倉賀野着は20時過ぎ。ココでなければ撮影出来ない列車だ。
16:17、新鶴見A81仕業、高崎操【臨単8876】倉賀野【臨8876】蘇我行きの石油返空。近年石油輸送列車はのきなみ臨時列車になっているが、臨時列車の癖に毎日運行されるという不思議な事が起こっている。
16:20、防護無線が発報された模様で、下り貨物列車が次々と目の前に停車する。JR機3兄弟が揃ってしまった。
55.40 10.3
「全通」という幻想について
4月7日![]() のこと・・・
のこと・・・![]()
(仕方なく、笑っ)三代目を聴きながら動画を撮ってみましたぁ~![]()
淡路島って同じ兵庫県やねんけど海を渡るから、なんかすごい旅行気分になれる
んよなぁ~って思ってる人も多いはず・・・。近いから泊まることもないけど・・・![]()
最初のトイレ休憩で淡路SAで下りたら、全通20周年記念イベントってのをやってて
ちょうど『ますだおかだ』が喋ってました(笑)興味ないから写真だけ撮ってすぐトイレへGO~っ![]()
さすが春休み中やから家族連れが多くてフードコートみたいなとこも座るとこない。
実はワタクシ同じ兵庫県民やのに『たこせんべいの里』に初めて行きました
和田山にあるしか行ったことないねん・・・
ここでも無料のコーヒーあったし・・・。でもソフトクリーム売ってなかったわ
そうや、パパが次は和田山のせんべいのとこまで行こかぁ~って言うてるわ
上のんは せんべい買ったらオマケで3つくれましたぁ~![]()
こんないっぱい買って誰が食べるねん?って感じやけど うちらが食べるねん![]()
そのあと『道の駅うずしお』に行きました![]()
ここ去年の今ぐらいに長女&次女ちゃんと女3人で淡路島に行った時にも行ったん
やけど、パパが行ってなかったから行ってみることにしましたぁ~![]()
あわじ島バーガーが食べたかったのにヤバいぐらいの行列やから断念![]()
※過去記事はこちら→
前に長女たちと行った時は、そんなに並んでなくて店内でも普通に食べれたのに
まぁ~~~、この日の行列は ほんまにヤバかった・・・。並ぶの嫌いや![]()
ライブに行った時のグッズ列やったら何時間でも並べるけどね![]()
でも この日は風が むちゃむちゃ強くて鳴門海峡のとこは怖かったわぁ~
しっかし同じ兵庫県内の淡路島にドライブしに行っただけで この土産
どこに配るねんっっって思ったやろ?これ全部 自分ち用です
あっ、淡路島牛乳カスタードロールってのだけは次女ちゃんの友達に渡しました。
そうそう前に社長の奥さんからもらった商品券6万円分![]()
�
��院に送って行ったり色々したから(多分)そのお礼やと思う。ありがたいな![]()
一枚も使わず置いてるんやけど これでスーツケースでも買おうかな![]()
※画像・動画お借りしました。
もうさ、ケンドンギュン・・・。ええわぁ~。ほんまに実現してほしいねんけど・・・![]()
サンギュンなんて一生懸命日本語を覚えようとしてくれてるのが伝わってくるし・・・。
ケンタとドンハン、ディズニーランド行って群馬にも行ってたんやねぇ~![]()
今日はパスポートをもらいに旧ヤマトヤシキまで行って、そのあと大好きなコムヒー
行って お茶タイムして、大手前公園付近をウロウロして帰ってきましたぁ~![]()
いったん家に帰ってから、今度は(次女ちゃんお気に入りの)加西のイオンに行って
きました。いやぁ~ほんま今日は むっちゃむちゃ疲れたわぁ~![]()
ではでは안녕
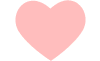
ついに全通の時代が終わる

全通 関連ツイート
安本「すごいチケ代だよぅ」
廣田「くじけちゃいそう…」
星名「諦めちゃダメ!」
松野「よし、全通だ!」
柏木「でも、お金払えなかったらどうしよう」
小林「だ、だ、だ、大丈夫だよ(;>_<;)」…