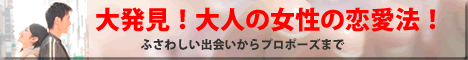全通がある
とし・バースデーライブ 開催決定!
とし・バースデーライブ
~みんなで祝おう!スーパープレミアムお誕生日会 ~
日時:2018年10月7日(日)~10月10日(水)
昼の部・夜の部
場所:オテル・ドゥ・ミクニ
7月28日(土)12:00より第1次お申し込みToshloveメンバー限定全通しチケット&各日通しチケット特別先行販売!
全通 暮らし・感じる・変えていく
1. 点線国道がなくなる
これまで、八十里越は旧道(トレイル)のみを紹介してきました。
今回は、工事のお手伝いをさせていただくことになり、工事用道路となっている既設の国道289号の一部と貫通した県境越えトンネルを抜け、クルマを使って八十里越を通り抜けました。国道の開通はまだまだ(未定 : 個人的な予想は2025年頃?)ですが、事実上点線国道はなくなっています。
工事区間は20.8kmとなっています。新潟県側の橋梁とトンネルは工事中で完成はまだまだ先になりそうです。
上の写真は2018年7月撮影。冬期の半年間ほど雪に閉ざされることもあり、じっくりと時間をかけて橋脚が伸びてきています。
下の写真は2016年11月、上の写真の反対側の旧道(トレイル)から撮影した写真です。
2.八十里越とは
実際の距離は8里(約31km)なのに、その険しさと山の奥深さゆえに、一里が十里にも感じられるほど急峻かつ長大な山道であることなどから、八十里越と名づけられたようです(諸説あり)。三条市下田地区から魚沼市の北端部を経由して只見町に至る街道で、番屋乗越、鞍掛峠(標高965m)、木の根峠(標高845m)の2箇所の峠があります。過去のブログでも紹介していますが、新潟県三条市、福島県只見町のどちらから歩いてもなかなかたどり着けない秘境中の秘境です。携帯電話はまったくつながりません。
2016年11月撮影の鞍掛峠
ある文献によると、戦国時代に越後・岩代両国間の交流が確認されており、その頃からこの険しい山に道があったようです。その頃から、会津から繊維原料、林産物、労働力などを越後へ、越後から食塩・魚類・鉄製品などの生活用品を会津に運ぶなど深いつながりがあったようです。この八十里越の繁栄は明治時代後期まで続いたようで、中越と会津を結ぶ重要な街道(年間約18000人が峠を越えたといわれている)として認識されていたようです。
大正3年に現在の磐越西線が全通すると、人々の移動や物資の輸送は鉄道へ移行し、鉄道網や道路網がその後全国各地で整備される一方で、八十里越は衰退の一途をたどったようです。昭和45年、吉ヶ平の集団離村によって歩く人はいなくなり廃道状態となってしまったようです。
下の写真の1.5車線の国道289号(現在は工事用道路)は、いつ建設されたのかわかりません。
3. 工事中の八十里越
上の写真の山を抜いているのが下の写真のトンネルで、すでに貫通しています。
現在はスノーシェルターの工事が行われています。豪雪地帯なので、橋梁やトンネルの他、雪対策の工事がまだまだ残っているようです。
工事中の風景、なかなか幻想的です。
忘れ去られたこの街道になぜ?再び道路を通そうなどと考えたのでしょうか?
戦後の高度成長期、日本列島を縦横に結ぶ道路網の建設が叫ばれはじめ、太平洋と日本海を結ぶ幹線ルートのひとつとして、この峠道が注目されたのでしょう、昭和44年11月に閣議決定、昭和45年4月1日に一般国道289号に昇格しました。
この八十里越の計画区間は、昭和61年度に直轄権限代行で事業実施に着手し平成元年度から工事が始まりました。
工事開始から30年、半年間雪に閉ざされることから実働15年ということになりますが、開通を待ち望んでいる地域住民の方にとっては「ほんとに開通するの?」的な事業だったのではないでしょうか・・・
この八十里越の道路は、ブナ林が素晴らしい守門岳、浅草岳、鳥帽子岳等がある越後山脈を貫きます。この豊かな自然は越後三山只見国定公園・奥早出粟守門県立自然公園・只見柳津県立自然公園に指定されており、イヌワシの繁殖が確認されるなど、それらに配慮しながら工事を実施しています。建設工事にあたっては、自然環境への影響を十分に把握し、適切な保全措置を行うために「八十里越道路環境検討委員会」が設立されています。
この道路に期待される役割は、①多彩な観光ルートの創出②災害時の代替ルート③第三次救急医療機関へのアクセス④物流の効率化などが挙げられます。
過去の重要な街道が点線国道になってしまった経緯を考えると、そのまま秘境中の秘境として残したほうが良いとも言えますが、新たな道路の誕生は、新たな便益をもたらします。造ると決めて造ったのですから再び廃道にならぬよう上手に使っていかなくてはならないですね。
県境のトンネルを抜けて会津側に抜けます。
会津側の工事はスノーシェッドや舗装などを残してほとんど完成しています。
モーターグレーダーによる路盤材の敷き均し作業です。この作業は熟練の技が必要ですが、徐々にICTによる自動化が進んでいます。(ここでは通常の施工)
工事用道路でも信号による片側交互通行が行われています。
会津側の道路(只見町内の区間7.8km)は、国土交通省ではなく福島県が事業を進めています。
入叶津道路と呼ばれるこの区間は1973年度に事業化され、トンネル2本、橋梁7本などの主要構造物は2004年度までに完成しています。但し、地元の方以外はクルマで通ることはできません。八十里越の旧道を歩く場合は、只見町側の浅草岳の登山口の駐車場でクルマをとめて旧道入口までひたすらアスファルト舗装の道路を歩くことになります。
この工事中の道路が開通すれば、新潟から南会津だけでなく栃木方面へのアクセスは抜群に良くなります。開通した頃に私は新潟にいないと思いますが・・・
4. 八十里越の先にある巨大ダム湖、田子倉湖
新潟県魚沼と福島県南会津の県境付近が、大電源地帯であることをご存知でしょうか?
阿賀野川水系である只見川の上流、奥只見ダムをはじめ田子倉ダム、只見ダム、滝ダムなど11の発電用ダムと14の発電所があり、その発電量が最大出力220万kWといわれています。あの黒四ダムの最大出力が33万5000kW、世界最大といわれる柏崎刈羽原子力発電所の1号機から7号機までの7基の合計出力821万2千kWという数字と比較すると、その凄さが理解できます。
なので、ダム湖の巨大さも半端ないっ!
そんな巨大ダム�
��をSUP(スタンドアップパドルボード)で探検します。
田子倉湖は、尾瀬湿原(標高1665m)を源にする阿賀野川水系只見川にある田子倉ダムの貯水池です。只見川の水はは伊南川と合流し会津盆地に入り、大川や日橋川(猪苗代湖)などと合流し、阿賀野川となって新潟市の日本海へと流れていきます。
朝、8:30にスタートしたのですが、山深い土地ということもあり気温差による風が吹き付けます。そして複雑な地形で風向きが一定でないこともあり、気をつけなくてはなりません。
何か気配を感じて山側をみてみると目の前にカモシカが佇んでいました。しばらくの間見つめ合っていましたが、やがてゆっくりと山の方へと登っていき、私に向かって石ころを落として(わざと後ろ足で蹴って?)、またしばらく私と見つめ合っていました。
しばらく漕ぐと、あいよしの滝が見えてきました。カラッカラの天気が続いており、ほとんどの沢が枯れている中でこの滝だけはいい音を奏でていました。
滝行を試みたのですが、冷たくてすぐ退散・・・
凍らせた「麦とホップ」が解けたのを確認してプシュッ!
この只見川付近では、昔から(明治40年代)電源開発地域として注目されていたそうです。
急峻な峡谷を狭い低地に向かって一気に流下する阿賀野川水系は、流量が多く水力発電に適した河川として早くから電源開発が行われており、第二次世界大戦後、復興期の経済拡大に備え、増加が見込まれる電力需要に対し検討された只見川電源開発計画を基に、昭和22年から本格的な電源開発が開始されたということです。
なんだか、ダム湖の水が電気に見えてきましたよ~
カルガモ?のヒナが仲良く泳いでいるのをそろ~とっ追いかけます。
私から少し離れた所に親鳥が心配そうにSUPに乗った怪しいオッサンを監視していました。
ダム湖なので基本的に沢のあるところには入り江があります。入り江に入るとカモシカに遭遇する確率が高まります(この日は2回)が、アブからの集中攻撃を覚悟しなくてはなりません。
そんなこんなで、電気を考える20km5時間弱のSUPツーリングを堪能しました。
全通空想実現百貨店
前作『いまさらですが』とともに、昨年もう一つ発足した新シリーズ『滋賀県』、長らく新作が出てなかったですが・・
放置してるわけじゃありませんw、着々と構想・計画はすすめております^![]()
今作第2弾として、県の北部にある長浜市を取り上げます。僕にとって大いに縁のある街(後述)で、あえてこれまで別荘ネタにはせず、温存していましたが・・
滋賀県シリーズも発足させたし、今回思い切って出す事にしました![]()
本作と次作の前後編2回で、長浜の街を歩きます![]()
今作ではまず施設訪問モノをやって、次作で街中を歩きたいと思います。
(※前後編2作で滋賀県シリーズの作ですが、内容から今作は『鉄道』にカテゴライズし、次作後編を『滋賀県』に入れます![]()
やって参りました、JR北陸線、長浜駅です。
東海道線米原駅から分岐して3駅目ですが、電車はほとんど大阪方面から直通しており、JR西が東海道線の滋賀県内に付けている愛称”琵琶湖線”の一部という実態です![]()
僕は30代の頃、この長浜に4年間住んでました。その頃はフツーのコンクリート駅舎だったんですが、近年、後程行く”旧駅舎”に合わせたレトロ調デザインに改築されてます。でも、周囲にいろんな建物が新しく出来てて、せっかくの駅舎がよく見えなくなってます![]()
(↑は、伊吹山口のバスターミナルから撮影、辛うじて駅舎の全体が撮れるのはここからだけ)![]()
駅舎は、南北に走る北陸線を跨ぐ造りで、その東西両方に出られます。東側が”伊吹山口”、西側が”琵琶湖口”です。
・東側は次作(後編)でやります。今作は旧駅舎へ近い琵琶湖口から出ます![]()
琵琶湖口側は、改築前の駅舎時代には改札はなく、旧市街地は主に駅の東側にあるため”裏口”的な感じです![]()
琵琶湖口から歩いてすぐ↑、旧駅舎が見えてきますが、その前にまず、春先のこの時期しかやってない長浜のイベント「盆梅展」をチラッと見に行きます![]()
(※取材は3月上旬)
盆梅展に行ったら↑、窓の外、国名勝の庭にも注目^![]()
慶雲館に隣接して、後年建てられたと思われる”新館”(?)へも順路はつづきます![]()
新館の盆梅もまた立派!盆梅のほとんどは地元・長浜の愛好家が栽培しているものです![]()
全部で数百鉢はあるでしょうか・
↑写真で香りをお届けしますw![]()
この”新館”には2階もあり、お茶席等があります。再び階段で1Fへ降りると土産コーナーがあって、そこが出口です![]()
(※靴は慶雲館入口で脱ぎ、渡されるレジ袋に入れて自分で持って歩きます)
土産コーナーは出口を出ても続きw、屋外には本物の梅の苗も売られています![]()
出口を出たところには、盆梅展のために一年間丹精こめて育てる過程が掲示されていました。↑看板によれば長浜市には約2000本の盆梅が育成されているとあり、日本最大規模だという事です![]()
庭にはいくつかの碑があるんですが、↑だけ紹介しておきます。
これは芭蕉の句碑で、”蓬莱に きかはや伊勢の 初たより”
(※意:正月飾りを眺めていると、伊勢からめでたい初便りが聞こえてくるようだ)
この碑、高さ約5mあり、日本最大の芭蕉句碑だとの事![]()
・・・・
さて、慶雲館の門を出ると、その真ん前には~
ドーンと構える、2階建ての洋館・・
これが旧・長浜駅舎です。
1882(明治15)年完成、1903(明治36)年に駅舎が現在地へ移転するまで使われて�
�ました。戦災も免れ、日本に現存する駅舎では最古のものです(鉄道記念物)![]()
最近この駅舎の裏手に新しい展示棟2棟が新築され、「長浜鉄道スクエア」としてリニューアルオープンしました。では入ります^^![]()
玄関を入った1Fは切符売場と改札があったスペースと、各等級の待合室があります![]()
明治期の駅の待合室は、等級別に分かれていました。昔の鉄道って、1等と3等では大変な違いがあったんです。現在の「今日はちょっと奮発してグリーン車にすっか!」どころじゃなかったそうです(笑)![]()
1・2等待合室は暖炉やソファーもあり、やや豪華な雰囲気w
なお、ここ長浜駅は東海道線が全通する前、長浜~大津間の琵琶湖を運航していた連絡船との接続駅としても賑わい、なので主要駅並のしっかりした待合室が必要だったようです![]()
荷扱い室には荷物の模型も置かれ、なかなかいい感じです^
駅長室も公開
ガラスケースに入って照らされている駅長の人形がちょっとコワい(笑)
僕が住んでいた頃(リニューアル前)は、この旧駅舎だけ単独で公開されていました。その頃は↑2Fに展示があったんですが、現在は新館に移されたとの事で、2階は閉鎖されています。
ではこれから、その新館へ行ってみます。改札口から通路が繋がっています。ここから先は僕も初めてです^![]()
前述の通り、新館は2棟あります。「長浜鉄道文化館」と「北陸線電化記念館」です。
・で、『なぜ、滋賀県北部の小さな街・長浜市がこんな力を入れた鉄道展示館を持っているのか?』とお思いでしょうけど、これから展示をご覧頂くと納得頂けます^![]()
まずは「長浜鉄道文化館」から![]()
木の骨組みが見えるドーム型の屋根が独特^
展示の内容は、勿論滋賀県の鉄道を中心としつつも、日本全体の鉄道網発展の歩みを重ねつつ紐解いていく格調高いものでした^![]()
・ではその次、”日本で3番目の鉄道”ってどこだったんでしょうか?
これについては『計画の順番』と『実際に開業した順番』が異なるため一概には言えないですが、計画ベースで言えば、明治政府は前述の新橋~横浜や大阪~神戸の計画時に、「京都~敦賀を結ぶ鉄道」も同時に決めていました。
太平洋側から日本海側へ抜けるルートとして江戸時代から重要視されていた、琵琶湖岸を通って近畿&東海から北陸へ続く要衝、ここ滋賀県に日本最初の鉄道計画のひとつが定められました![]()
そして、その始発ターミナルとして建設されたのが、この旧長浜駅だったんです。
1882(明治15)年に長浜~敦賀間が一部のトンネル部を除いて開業しました![]()
(※但し、実際に開業が早かったのは1880・明治13年に開通した北海道の手宮線でした)
東海道本線は、この当時の時点で名古屋~京都間は中山道ルートで建設される事が決まっており、長浜駅は東海道と北陸を結ぶ結節点として重要な位置にありました。
また↑のパネルの通り、長浜~大津間は鉄道開通までの間、琵琶湖を連絡船で結んでいました。日本最初の鉄道連絡船は、海の無い滋賀県で始まったんです![]()
ここで『え、じゃあ米原駅は?』と思われたかたもおられるでしょうが、東海道線は当初米原は通らず、関ヶ原から長浜までを通る線が先に敷設されました。今では痕跡も残ってませんが、明治期には長浜からまっすぐ東へ鉄道が延びてたそうです![]()
その後、現在の関ヶ原~米原ルート開通に伴い長浜ルートは廃止され、連絡船だった大津~米原~長浜間も鉄道開通、米原駅が東海道と北陸のジャンクションとなりました![]()
長浜駅は、我が国鉄道草創期の歴史をまさに地でいくような履歴を短期間で重ねた後、米原駅にその地位を譲って中間駅となっていったんです・
・いかがでしょうか、これで『なぜ長浜に、最古の駅舎や本格的な鉄道博物館があるのか?』がおわかり頂けたと思います^![]()
つづいては・・
展示後半は、北陸本線全体の話になってきます。
・日本初の本州横断路線たらんと開業した北陸線、戦後もこの線では『日本初』の偉業が2つありました。
まず1つは「北陸トンネル」の建設![]()
北陸線の敦賀~今庄(福井県南部)は海岸ギリギリまで山また山の急峻な地形(※当別荘で14年7月にupした「福井ツーリング」をご覧頂くとよくわかる)で、開通時はその山中を縫いながらグニャグニャと走っていました。また急勾配な上、途中4ヵ所のスイッチバックもあったそうで、非常に輸送上のネックになっていたとの事![]()
そこで同区間を一気にトンネルで越えて�
��まおうと、1962(昭和37)年に開通したのが北陸トンネルです。長さ約13km、現在でも在来線の単独トンネルとしては日本最長のはずです。僕も何度かここを列車で通過しましたが、ホント「いつになったら出るのか」と思うほど、時間の流れを遅く感じるトンネルです(笑)![]()
↑は北陸トンネル開業に伴う時刻変更を告知する当時の敦賀駅看板ですが、敦賀から「上野行」や「青森行」ってあったんですね~(驚)
そしてもう1つの”北陸線が日本初”は「交流電化」![]()
日本の鉄道電化は元々、モーターが回しやすかった直流で始められ、現在も首都圏や京阪神等の通勤電車はほとんど直流です。しかし、電力会社から買う電気は交流で配電されてくる為、変電所で直流へ整流しなければならず、その整流や架線への送電時に生じる電力のロスが早くから指摘されていました![]()
そのため国鉄では『交流のまま電化してモーターを回す研究』に取り組み、まず東北の仙台~山形を結ぶ仙山線で実験を開始。仙山線もそのまま交流で営業運転を始めましたが、営業線として初めて本格的に交流で電化したのがこの北陸線です。
1957(昭和32)年、田村~敦賀間が交流電化。仙山線&北陸線の交流電化が順調に運用されたのを機に、北海道・東北・九州の各路線も交流で電化される事となり、その成果としてアノ東海道新幹線も交流電化で造られました。↑にある新幹線のオモチャも理由あって置かれてる(?)んです![]()
そんな、先進の歴史を歩んできた北陸線ですが、平成になりJRへ転換されても進歩は止まりません^![]()
京阪神からの快速電車を直通させるため、交流だった区間の一部を直流化するという、これまた全国初の試みを実行。これにより長浜への観光客がドッと激増しました(※この直流化については、次作の長浜街ブラで詳述します)
・文化館さいごに、この写真をご覧頂きます↓
1957(昭32)年10月1日、木ノ本駅で行われた電化開業式の様子。
戦後復興を成し遂げ、オリンピックや新幹線建設も決まって元気があふれていた当時の日本、真新しい機関車に人々が喜びの声を上げています。当時の熱気が伝わってきそうな感動の一枚です![]()
・そして、↑の写真に写っている当時の最新鋭機、ED70 1号機が、なんと隣の建物、北陸線電化記念館に保存されています![]()
文化館を出て、隣の建物のドアを開けると・・
お・・
お~~
半世紀前、人々の期待と熱気の中デビューした、交流電化1号機が目の前に・![]()
このED70、1975(昭和50)年まで活躍した後引退、敦賀の機関区で保管されていましたが、ここがリニューアルされた際に修復・長浜へやってきたとの事です。隣のSL・D51と2両で展示されてますが、なんか老夫婦が仲良く並んでいるみたいで、いい感じです^![]()
運転台も見学できます
当別荘ではこれまでにも数々の鉄道博物館で運転台へ登ってますがw、やはり『車両って運転してナンボ』のものですから(笑)、一番往時の事を想像して楽しめるのが運転台ですね・^![]()
↑は金沢のJR工場で修復され、長浜へ運ばれる経過を紹介するパネル。この長浜保存実現には、大井川鉄道の車両保存等も手掛けている公益財団法人が尽力したそうです。ED70は計19両製造されましたが、保存されているのはこの1号機だけで、大宮や京都の鉄博にも無い貴重なものです![]()
全通の置かれている状況をもう少し理解してもらいたい
——————-
生メールやってます!!
毎日3通!!(日によっては泣く泣く2通の日も…ごめんね…)
鈴木の日常のどうでもいいことからビックニュースまで鈴木らしく
最近生メールの本質を見つめなおして「彼女(面)メール」
ぜひ生メ登録してほしいな!
鈴木の彼女(面)メール受け取ってね!!
↓↓
twitterもやってるよ!フォロワー2000人目指してます
リプも全部読んでるよ!
↓↓↓
——————
アイカレは9/29から9大都市ツアーがスタート!!
9大都市ツアーのファイナルは12/9TDCホール!!
すでに発表されているYOZORAのMV撮影企画など、9大都
ファイナルのTDCホールは絶対絶対来て欲しい!
来ないと損するようなライブにします!!
UC2としては、9/19から定期公演『UC2戦国物語~
毎公演毎公演1つずつチャレンジがあります!!
どこか一つだけ来ても楽しいけど、全通するともっと楽しい!
どちらもチケットはコチラから↓↓↓↓
あの直木賞作家が全通について涙ながらに語る映像
本日は夕方から殺陣付け稽古。
みんなのいい顔が
ジーナ役のれい姉さんも
みんな良い顔☺︎
【チケット取扱い】
amipro/CNプレイガイド
➡インターネット予約
cnplayguide.com/amitike/
➡電話予約:0570-08-9999(10:00~18:00)

全通 関連ツイート
2018ˉⰨ
115系 R-01 当駅止
最近まで代走運用がメインで中々撮る機会がなかったですが、今日ようやく撮れました。
何とか山陽本線が全通するまでに記録できて良かったです。 https://t.co/T8bsqZvjis